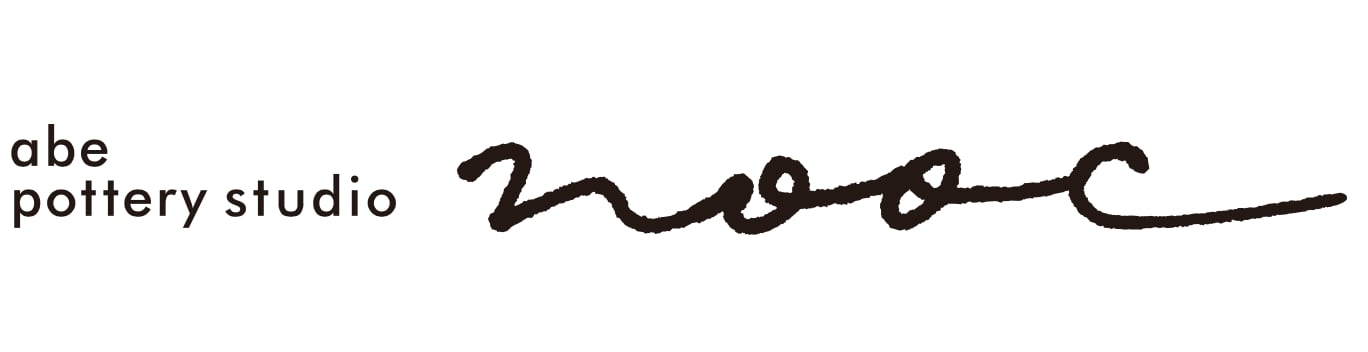2024/06/13 22:57
今日は今月予定しているイロドリさんでのオンライン個展用の作品を発送しました。
(詳細が決まりましたら改めてお知らせさせていただきますね。)
木曜日は出勤スタッフが少ないので間に合うか不安でしたが
最後はちょっとしたスポーツを終えたような疲労感で、なんとか配送業者さんに手渡せました。
全て割れ物ですからね。
梱包作業は工房内で行う本当に最後の工程で、
半端な梱包で配送中に割れてしまうと水の泡です。
かといって過剰な梱包は環境負荷的な面でもどうなんでしょう。
嵩張ってしまい当然ながら送料に跳ね返ってもきます。
海外に発送する時はさらに気を使います。
意外と奥の深い梱包のセカイ。
+ + + + +
下半期の展示に向けて、新しい型作りをはじめました。
お皿類は石膏型で作ることが多いのですが
型のベース部分(加飾のないプレーンな状態)は
近くの笠間陶芸大学校の設備を借りて作っています。
石膏を水で溶く際に手で撹拌すると
どうしても液中に気泡が入ってしまうのですが、
大学校には真空で撹拌できる機械があり、
その機械を使って気泡の入らない石膏型を作っています。
気泡が入ると型の表面に気泡痕が残ってしまいスムースな表面が得られなくなります。
大学校は教育がメインの場ではありますが
外部への設備の時間貸しも行なっていて、
我々窯業関係者も時々利用させてもらっています。
これも産地ならではのものだと思います。

無事型のベース部分は出来ました。
この後工房に持ち帰り、制作の合間をみて
少しづつ彫刻刀で加工していきます。
ものにもよりますが回転体でシンプルなものでしたら2.3日、
レリーフのあるものや非回転体だと7日くらいかけて完成させます。

+ + + + +
型作りは日常的に行なっているものではありませんが
工房内でも私しか関与しない領域のひとつであり、
その後出来上がるものに広く影響を及ぼすとても大事な工程です。
現在は3Dプリンターで作るのも工業製品では一般的ですが
笠間や益子では聞いたことがないですね。
かつては益子におそらく最後の成型所がありましたが
5.6年前だったか、ご高齢のため廃業されました。
型作りもそれだけで専門職として成立する奥深いものです。
私自身は見よう見まねで覚えた部分が多く、
発見の連続でここまでやってきました。
石膏は粘土とは素材の特性が全く違うので、
同じように考えてはダメです。
石膏と粘土、素材としては実は石膏のほうが好きです。
理由としては
カタチを作ったらもう動くことがないから。(焼き物は焼成で収縮したり歪みが生じる)
時間をかければかけるほど基本的にはキレイな(滑らかな)ものができるから。
年単位で寝かせてもまた途中から普通に再開できるから。
まぁ石膏ばかり触っていてもダメなので、
ロクロやったり、絵付けしたり、指導したり、経営的なとこしたり
こんな時間までパソコンを開いているのが日常なのであります。