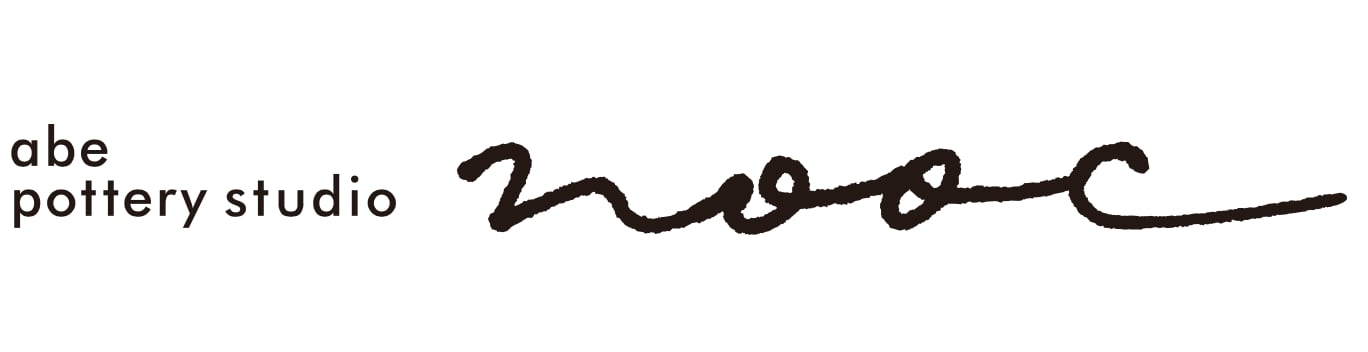2024/07/13 10:02
そろそろ梅雨も終わりに近づいているのでしょうか。
作ったお皿やカップの乾燥はこの時期すこしゆっくりになります。
陶芸では粘土の乾燥具合に応じて、できる作業や向いている作業があります。
例えばロクロを挽きたての柔らかい状態だと、
お皿の口の部分を何箇所か竹串などで押して輪花(お花の形)に成形したり、
すこし全体の水分が飛び、軽い力で押しても変形しなくなったら高台(器の裏面)削り。
そこからさらに乾燥が進んでからやる加飾もたくさんあります。
乾燥のスピードが早いと作業も慌ただしく、やりにくい作業も出てくるので
乾かないように養生しながら、乾燥速度をコントロールします。
ビニールや新聞紙、それらの併用など、養生に使う素材の使い方も大切です。
自然乾燥といっても素地の厚みや粘土の種類といった素材由来のものや、
気温や湿度、風の流れ、ストーブやエアコンなどの冷暖房機器などの環境由来のもの、
いろんな要素が絡みます。
最終的には経験から乾燥速度を予測して段取りを決めています。
これから夏になると気温も高くなり、乾燥速度は一気に上がります。
四季のある日本では特に季節に応じた対策が必要になりますね。
+ + + + + +
大阪の趣佳さんでの企画展のおしらせです。
「みんなの輪花展」という企画展で、13名の作家の輪花の器が揃います。

ウチでは普段、輪花の器を作るときは石膏型成形が多いのですが
今回はロクロでやや厚めに挽いた素地を削って輪花の酒器や花器、ふたものも制作しました。
どれも違ったカタチで、一点ものとして作りました。
ひらひらしていたり、捻れていたり、すこし動きのあるカタチです。

趣佳さんのインスタグラムで他の作家さんの輪花も見られます。
陶芸の世界では大昔からある加飾のひとつかと思いますが
やっぱりそれぞれで輪花の取り入れ方が違いますね。


お近くにお出かけの際はぜひお立ち寄りくださいね。
会期は7/21まで、どうぞよろしくお願いいたします。