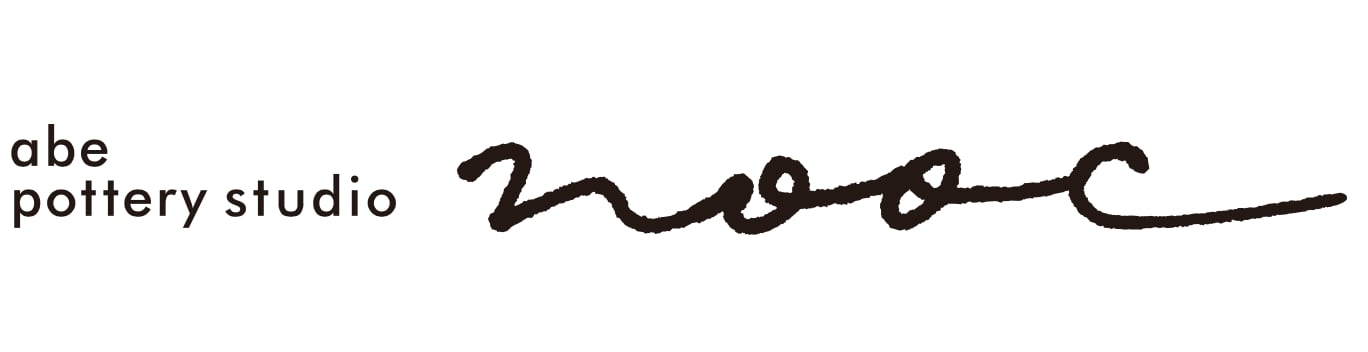2025/03/17 10:36
昨日の午後からの窯焚きで久しぶりに工房泊でした。
夜中、窯が落ち着いたところで一度寝袋で仮眠するのですが、凍えるほどは寒くない。
春が近づいていることを感じた瞬間なのでした。
+ + + + +
3/20春分の日からはじまる兵庫県芦屋市のabundante(アバンダンテ)さんでの個展のおしらせです。
新作もいろいろ準備中ですが、そのひとつがレンゲです。
今年でちょうど陶歴としては20年になります。
20年やっていてレンゲを作ったのは初めてです。

ブログではおしらせできておりませんでしたが
すこし前に台湾スイーツの豆花をテーマとした企画展にお誘いいただき、
その際に豆花用にボウルとレンゲを制作するはずでした。
そのときはレンゲの焼成に失敗し、ボウルだけの出品になりましたが。。
その後、焼成方法を見直し再チャレンジ。
きちんと歪みなく焼き上げることができるようになりました。
衛生面や強度面からレンゲ全体に施釉したかったので、
持ち手に開けた穴に棒を通して窯の中で吊るして焼くことにしました。
穴の中だけは無釉になりますが、この方法なら全体に施釉することができます。

窯から無事出てきたときはまたすこし素材や焼成のことが分かったような気がして
焼き物をやっていて面白いと思う瞬間のひとつです。
+ + + + +
流れで駒澤大学の陶芸部に入ることになり、そこで初めて土に触れたのが19歳の春。
そのときは正直そんなに面白いとは思いませんでした。
行くところもなかったし、先輩が面白かったから着いて行っただけでした。
しばらく週1.2回くらいのペースで部室に通っていたら
前回はできなかった土練りやロクロの上で中心を取ることがすこしできるようになっている。
また翌週には径が10cmくらいのものが一人で挽けるようになっている。
GW前には初めて釉薬をかけて灯油窯で焼いてもらい、
作ったものが器として焼き上がって、下手かもしれないけど普通にそれでお茶が飲める。
こういうのを重ねて素人なりにだんだんできることが増え、
自分が作ったものが普通に使える、というところが19歳の阿部青年には何か刺さったんですね。
GWごろにはもう夢中になっていて、週6.7回くらいのペースに変わり
がむしゃらに作り、部室にあった作陶や釉薬の教本を読み漁り、先輩の作り方を見て教わりました。
今振り返っても、美術系でもない普通の大学生にしては上手な先輩が多かったです。
指導者はなく、先輩やOBが下の世代に教えていくスタイルでした。
飲み会の隅っこで互いの陶芸論をぶつけて喧嘩したり、
なんだかちょっと昭和で、体育会系っぽくて(ビールの注ぎ方から教わったり...笑)、
でも先輩方は褒め上手な方が多かったのも、夢中にさせる要因のひとつでした。
日本や中国・朝鮮の古陶の図録や、昭和の大陶芸家の作品集も片っ端から読みました。
これらは現在の制作にも大きな影響を与えています。
大学の図書館にも専門書がなぜか揃っていたので、授業にも出ずそれらを研究しました。
(3留への道を歩み始めたわけです。)
そして作家の器、というものを初めて買ってみたり。
初めて買ったのは田村一さんのしのぎの入った白い飯碗で、当時は益子で制作されていた方です。
たまたまなのですが田村さんも確か大学の陶芸部出身だったはず。
この業界では私と同じような、大学の陶芸部出身という方にたまに出会います。
別の時期に別の大学で陶芸と出会っているのですが、割と似たような経験をしているというのが不思議です。
+ + + + +
今も作っては失敗してを日々繰り返しています。
今なお夢中でやっていられるのは昨日できなかったことができるようになったり、
分かりやすく自身の成長が感じられる、という点が大きいかもしれません。
それによって新しい作品をまた作り出すことができ、
やがてそれもスタンダードになり、また次の新しい作品を模索し始めます。
その繰り返しで20年が経ちました。
19歳の阿部青年は20年後の自分がまだ土をいじっているとは思っていなかったでしょうが。。
昭和の大陶芸家が遺した有名な言葉
「新しい私が見たいのだ、仕事する」