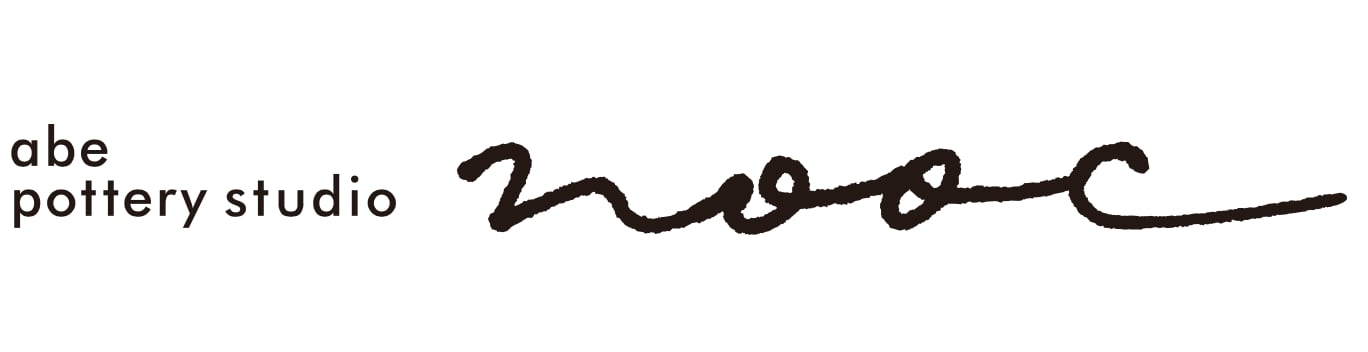2025/09/16 22:44
お洋服のメーカー、45Rさん別注のうつわのラインができました。
9月20日から45R大阪髙島屋店にてご覧いただけます。

+ + + + +
最初の出会いは昨年10月、西麻布の桃居さん。
ちょうど個展会期中に社長さん、副社長でデザイナーの井上保美さんにお越しいただいたのがきっかけでした。
お話を伺っていくと工業製品としてではなく手仕事のものとして、オリジナルのうつわのラインを作りたい。
これまでの洋服作りのテーマでもある、海と山をイメージしたものを作りたい。
それらを形にしてくれる作り手を探しているとのことでした。
まずは素材の違うお互いのものづくりを知るところからスタートしました。
笠間の工房にお越しいただいたり、私が青山の本社に伺ったりしながらサンプルのやり取りが始まりました。
その打ち合わせのなかで保美さんの私物の古いヨーロッパ陶器や、
45Rさんのこれまでの絵刷り(生地の柄を紙にプリントしたもの)のファイルを見せていただいたり
うつわ作りのヒントも得ながら進めていきました。
+ + + + +
工房では素材のテストからはじめました。
普段は基本的に半磁器で制作しているのですが、
今回は陶器で作ってみようと考えました。
半磁器は陶器に比べると堅牢でよく焼き締まり、経年変化も起きにくい素材です。
45Rさんの洋服作りのなかに経年変化というキーワードがあり、
例えばデニムなど、着古していくことで自分だけの1着に育っていくという考え方です。
うつわも同様に使っていくことで育つ、という考え方があり、
それは貫入へ色が入っていくことだったり、茶渋がついたり、
使っていれば当然欠けちゃったり...少しづつその家の表情のうつわになっていきます。
今回はあえて経年変化の起きやすい陶器で出発することに決めました。
経年変化の楽しめる、経年変化が起きたときに嫌じゃない感じを想像しながら進めます。
半磁器は基本的には白土ですが、陶器ならその辺りは自由自在。
白、赤、黄、茶、黒...顔料や酸化金属を練り込めば紫だろうが緑だろうが何色でも。
陶器を扱うのは大学以来。
いろんな粘土をブレンドしたり、テストを重ねました。
骨格として扱いやすく万能な信楽の粘土をベースに、
堅牢さを与えるために普段工房で使用している3種ブレンドの半磁器土と
素地に表情をもたらす地元笠間の粘土を加えた45Rさん用の粘土を新たに作りました。

+ + + + +
釉薬は大昔からある藁灰釉(わらばいゆう)を使うことにしました。
これは保美さんから見せていただいたドイツ製の古いマスタードポットの肌あいを参考に。
一番近そうなのが藁灰釉を薄くかけたときの表情でした。

そのマスタードポットは少しざらつきのある釉層の薄いものでした。
推測ですが、人力で大量に作って出回っていたいわゆる生活雑器で、
釉薬を薄くかけることで釉薬の消費を節約し製造コストを抑えたり、
現代だと釉薬の粒子を細かく擦り潰し、篩(ふるい)を通して滑らかな肌あいにするところ、
時間的コスト面から省いていたのではないかと...。
しかしその少し荒っぽさのある肌あいが素朴さにも繋がっているようにも感じました。
茶色っぽくなりがちな普通の家庭料理には土っぽく、素朴な肌あいがとてもよく合います。
あえて少しざらつきのある昔ながらの薄い藁灰釉にたどりつきました。
厚めに釉薬のかかったところは少し白く乳濁し、藁灰釉本来の表情を見せます。
+ + + + +
最後に加飾の部分。
海のシリーズではうつわに大きく、おおらかに瑠璃釉でイカリマークを入れました。
これは前述のマスタードポットに描かれたイカリらしきものや、
45Rさんの洋服のなかでもよく使われているモチーフだったから。

陶磁器の絵付けには通常は専用の絵の具を使います。
ブルー系の絵付けだと呉須というのを使うことが多いです。
今回は呉須から作った瑠璃釉で書道のように大胆に、一息に図柄を入れました。
釉薬で描いたので通常の絵付けと違ってぷっくりと手触りがあり、
焼成で少し図柄に動きが生まれ素朴な雰囲気です。
初めの頃は焼成で図柄が動き過ぎて文字が判読不能になったりしていたのですが、
発色は変えず、釉薬を固く(溶けにくく)することで動きをほぼコントロールできるようになりました。
(陶芸の学校では釉薬を専攻していたのでこの辺りは専門分野なのですヨ)
+ + + + +
山のシリーズではアビニヨンと名付けた草花の図案で覆い尽くしました。
もちろん全て手書きなのですが、細いアウトラインを描くために漫画家の使う丸ペンと着彩には面相筆を併用して描いています。
このアビニヨンは45Rさんの絵刷りから、それを再解釈して作った図案です。
私の作品としては初めて赤を取り入れた図柄にもなりました。

アウトラインを描き終えたらいよいよ着彩していくのですが、
赤って小さな面積でもすごく効くんですね。
黄色や水色の花も散らしつつ、バランスよく赤を効かせ、
面積としては一番大きなグリーンには新たに調合したティールがかったグリーンを。
この絵付けの工程が最も大変でしたが、カラフルで楽しいうつわができました。
すこしヨーロッパ更紗のような図柄でもあり、うつわが育ってくるのも楽しみです。
+ + + + +
保美さんが見せてくれた古いうつわに共通していたのは
特別なものではない、ということ。
作家業をやっていると他との差別化の意味でも、独自の技法やフォルムはその作り手の大きな武器になりうると思います。
でも今回は「どうだ、こんなの見たこともないだろ〜!」的なものではなく、
あくまでも生活雑器としてのうつわ、普段の食卓に馴染むうつわなのではないかと思うのでした。
うつわのカタチも気をてらうことなく、シンプルなものを心がけました。
基本のロクロとシンプルな型作りです。
最初のお披露目は45R大阪髙島屋店になります。
私も初日は在店させていただきます。
海と山のうつわ、ぜひお手に取ってご覧くださいね。
45RさんのHPでも紹介してくださっています。
内容が重複するところもありますがよかったら。